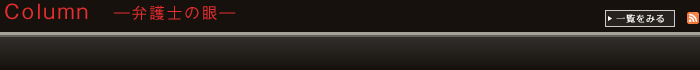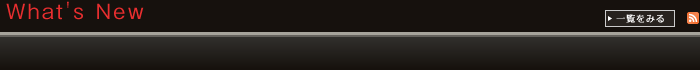2024.04.08
最近の裁判例から
特別養護老人ホームに入所していた高齢者(当時81歳)が、食事中、口の中に食物を含んだまま動かなくなり、その後職員が食物を吐き出させたのですが意識不明となり、その日のうちに亡くなるという事故がありました。
そこで亡くなられた高齢者のお子さんが、老人ホームを経営していた会社を訴えました。
裁判所は、老人ホーム側の責任を認めたのですが、この高齢者に対しては、嘔吐したりむせにくい食事にしていたところ、家族の希望により普通の食事に戻したといった事情があったことから、賠償額を5割差し引いたというものです。
こうした高齢者施設における事故は数多くあるのですが、責任の有無や程度は、各事例毎に詳しく検討しなければなりません。
相談を希望される場合はご連絡下さい。お待ちしています。
(八十島 保)
2019.11.07
相続に関する法律が改正されました⑨
遺言には、特別な場合も含めいくつか方式が法律で決められており、それに従う必要があります。
今回、自筆証書遺言について改正がなされ、2019年1月13日から施行されています。
自筆証書遺言とは、遺言者が、全文、日付及び署名を自ら手書きし、印を押したものです。
全文ですので、これまでは、財産目録も全て手書きでなければならず、パソコンで作成したものや、通帳のコピーを添付しても有効な遺言書とは認められませんでした。
しかし、自筆証書遺言をより使いやすくすることにより、その利用を促進する目的で、本文に添える財産目録については手書きでなくても良いことになりました。但し、偽造や変造を防止する観点から、目録の各頁に署名し印を押す必要があります。 (八十島 保)
2019.09.26
相続に関する法律が改正されました⑧
前回ご説明したように、遺産分割前であっても、一定の限度で預貯金の払戻しを認める制度が設けられました。
しかし、これでは不足する場合はどうしたら良いのでしょうか。
家事事件手続法200条3項に、遺産分割の審判または調停の申立があった場合は、家庭裁判所は一定の事情により遺産に属する預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができると定めています。
他の共同相続人の利益を害する場合は認められませんが、急迫の危険を防止するため必要があるときといった事情がなくても、払戻しが認められることになります。
但し、これはあくまで仮に取得させるものですので、後の遺産分割には影響しません。
(八十島 保)
2023.12.22
年末年始の休業について
本年の営業は12月28日(木)正午までとなります。
新年は令和6年1月9日(火)午前9時より営業いたします。
2023.08.09
夏期休業のお知らせ
令和5年8月14日(月)・8月15日(火)は休業させたいただきます。
2020.05.11
新型コロナウイルスの影響について
事業者の皆様は、現在の新型コロナウイルス及びこれに伴う緊急事態宣言により、多大な影響を被っておられると思います。
このような時には、収入を確保し、支出を抑制し、正常に戻るまで資金繰りの目途をつけることが一番重要です。
その入りと出について、お悩みはありませんか。金融機関や取引先との交渉がうまくいかないということはありませんか。またそもそも資金繰りをどのように確保してよいか悩んではいませんか。
これまで弁護士に相談したことがない方もこのような緊急事態ですので、是非、我々弁護士を利用してみて下さい。
この関係の相談には、相談料無料で対応します。